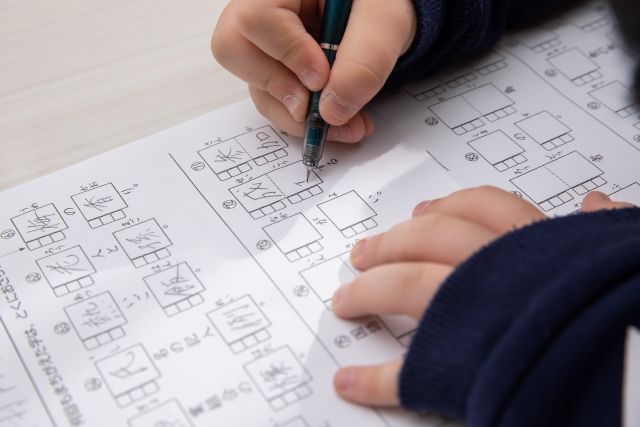日本語で「づらい」と「ずらい」の使い方について、選択に迷うことがよくあります。
これらの表現は、日本語学習者や日常会話の中で使う人たちにとって、しばしば混乱の原因となります。
似ているようで微妙に異なるこれらの言い回しは、どのようにして適切に使い分けるかが重要です。
この記事では、両表現の違いと正しい使用方法を、具体的な例を用いてわかりやすく解説します。
「行きづらい」と「行きずらい」の正しい使い分け

「づらい」という表現は一般的に正しいとされています。
例えば、「行きづらい」とは、「行く」に「つらい(辛い)」が合わさり、動くことが困難である状況を示します。
この文脈では、「ずらい」という言葉は通常使われません。なぜなら、「つらい」を「ずらい」と表現するのは一般的な用法ではないからです。
「づらい」と「ずらい」の違い
どちらの表現を使うべきか迷うときは、言葉を分解して考えると良いでしょう。
「行きづらい」は「行く」と「つらい(辛い)」が結びつき、「づらい」を使うのが適切です。この形は「動くことが辛い」という意味になります。
一方で、「行くのがすらい」という表現は一般的には使われません。また、「つらい」という言葉は、「からい」と同じ「辛い」という漢字で表されることもあります。
「づらい」と「ずらい」の違いと使い方について

「づらい」と「ずらい」は意味が似ていて、時として「づ」と「ず」の発音を区別するのが難しい場合があります。
例えば、「これ読みづらいな?」と「これ読みずらいな?」という言葉の発音の違いは微妙で、聞き分けるのが困難です。
理論的にはどちらの表現を使用しても間違いではありませんが、一般的に「〇〇+辛い」の形をとる場合は「づらい」を使うのが通例です。
「~づらい」という表現は「~辛い」と表記され、『新明解国語辞典』(三省堂)では以下のように定義されています:
「~づらい」は、何かを行いたいと思ってもスムーズに事が進まない状況を指します。
パソコンとスマートフォンでの「ずらい」の入力について
スポンサーリンク
パソコンで「ずらい」と入力すると、多くの場合自動的に「づらい」に訂正されます。
しかし、スマートフォンでは自動変換が正しく機能しないことがあるため、「ずらい」と表示されることがあります。
このため、SNSなどでは「ずらい」という表記が増えており、一部の人々にはこの表記の方が自然に感じられることもあるでしょう。
どちらを使うべきか?
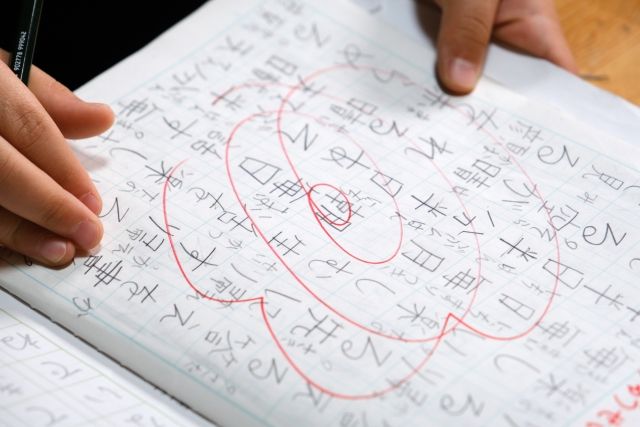
「づらい」と「ずらい」の選択に迷うときは、一般的に「づらい」の使用が推奨されます。
しかし、「ずらい」も間違いではなく、特にSNSでよく見かけるようになり、今後主流になる可能性もあります。
まとめ
この記事では、「づらい」と「ずらい」の使い分けについて詳しく説明しています。「づらい」は通常、「〇〇+辛い」を組み合わせた表現で用いられるのが一般的です。
ただし、発音が似ているため、デジタル入力時には「ずらい」と表示されることがあります。
日常会話ではどちらの表現も通じますが、公式な文書やフォーマルな場では「づらい」を選ぶことが良いでしょう。
言葉の使い方は時代によって変わりうるため、現在の傾向と正しい用法を理解し、適切に使い分けることが重要です。