メールやチャットで「連携を取る? 図る?」と手が止まったことはありませんか。
似ている二つの言葉ですが、実は役割がまったく違うのです。
本記事では、プロセス=図る/結果・接触=取るというシンプルな軸で、例文や言い換え、誤用を避けるコツまでやさしく丁寧に解説します。
初めての方でも安心して読み進められるよう、女性目線で読み手に寄り添う表現を中心にまとめました。
まずは1分で違いをつかみ、次にビジネスと日常の具体例でしっかり定着。
最後にクイズとチェックリストで仕上げれば、今日からの文章がぐっと伝わりやすくなります。
迷ったら、ここに戻って一緒に整えていきましょう。
はじめに:なぜ「図る」と「取る」は混同される?

混同の背景をやさしく整理
言葉としての「図る」と「取る」は、どちらも会話でよく登場しますが、実は役割がまったく違うのに、音が似ていて文脈も近いため混同されがちです。
さらに「測る・計る・量る・図る」の同音語が多いこと、職場では結果を早く示したい空気があることも影響します。
本記事では、初心者の方でも迷わず選べる判断軸を用意し、使い分けのコツを具体例たっぷりで解説します。
この記事のゴール
まずは結論を先にお伝えします。基本は「プロセス=図る」「結果・接触=取る」です。
合意や関係を良くしていく“道のり”を述べたい時は「図る」、承認や連絡など“手に入れる・つながる”場合は「取る」。
この軸を頭に入れておけば、メールや議事録、チャットでも表現が安定します。
読み終わる頃には自信を持って言い換えができるようになります。
「図る」と「取る」の違いを理解しよう
「図る」とは?定義とやさしい使い方
「図る」は、物事を計画・企画して実現に近づける意味です。
相手との調整や合意形成、改善の推進など、まだ結果が出ていないプロセスそのものを表します。
例)「関係強化を図る」「再発防止を図る」。
ゴールに向けて準備し、関係者と歩調を合わせるニュアンスがあるため、丁寧で前向きな印象になります。
女性らしい柔らかさを出すなら「円滑化を図る」も素敵です。
「取る」とは?定義とやさしい使い方
「取る」は、必要なものを手に入れる・選ぶ・連絡を交わす意味です。
相手の承認を得たり、窓口に連絡したり、休暇や席を確保するなど、具体的な結果や接触に焦点があります。
例)「連絡を取る」「許可を取る」「休暇を取る」。
行動がはっきりしているため、読んだ人に次の動きが伝わりやすいのが特長です。
依頼メールでは「ご承認を取れ次第、進めます」が自然です。
基本の違いをひと言で
使い分けに迷ったら「これは準備や促進?それとも獲得や接触?」と考えます。
準備・促進なら図る、獲得・接触なら取る。
さらに、相手から“もらう”感じが強いとき(了承・許可・連絡)は取る、こちらから“整えていく”とき(理解・関係・改善)は図るがぴったり。
まずはこの一本線の軸を覚えておけば、ほとんどの場面で迷いません。
よくある混同ポイント(誤用注意)
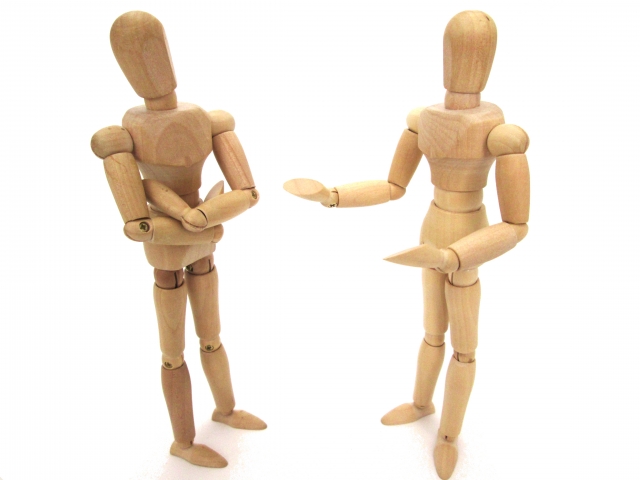
「理解を図る」vs「理解を取る」
「理解」は相手の気持ちや認識を深めてもらう過程を指すため、「理解を図る」が基本です。
「理解を取る」としてしまうと、まるで“理解という結果を受け取る”ような印象になり、少し不自然です。
提案時は「まず背景共有を行い、理解促進を図ります」が丁寧。
相手の合意が必要な場面では「了承を取る」に言い換えると、意味の違いがさらにクリアになります。
「連携を図る」vs「連携を取る」
公的・硬めの文書なら「連携を図る」が無難です。
プロジェクト運営や部署間調整など、仕組みや関係を整える場面に合います。
一方、口語や社内チャットでは「連携を取る」もよく使われますが、この場合は「連絡を取り合う」「一時的に協力する」ような接触のニュアンスが強め。
文体と場面に合わせて選び分けるのがコツです。
固定表現に注意(図るでは言えないもの)
「連絡を取る」「許可を取る」「休暇を取る」「記録を取る」などは固定表現として定着しています。
ここを「図る」に置き換えると不自然なので注意しましょう。
逆に「関係強化を図る」「効率化を図る」「再発防止を図る」は図るの定番。
迷ったら、接触・獲得=取る/促進・改善=図るの基本に立ち返れば安心です。
コミュニケーションにおける使い分け
「図る」を使うとき(合意形成・改善・関係づくり)
チームや取引先とより良い状態へ近づくプロセスを説明するときに向いています。
例)「合意形成を図る」「円滑な情報共有を図る」「品質向上を図る」。
読み手は“今は準備・調整の段階”だと理解でき、プレッシャーを与えすぎません。
メールで柔らかく伝えるなら、「まずは理解の促進を図りながら、無理のない進め方を検討します」が好印象です。
「取る」を使うとき(連絡・承認取得・選択)
スケジュール調整や稟議、申請など、はっきりしたアクションを示したいときに有効です。
例)「先方へ連絡を取る」「上長の許可を取る」「別案を取る」。
読んだ人が次の手順を想像しやすく、行動の責任範囲も明確になります。
「本日中にお時間を取る」「承認を取れ次第ご連絡します」など、期限や条件と組み合わせると効果的です。
使い分ける理由(読み手の安心感と記録性)
文章の目的は、読み手に正しく伝わり、安心して動いてもらうこと。
プロセスと結果が混ざると、期待値がズレたり、記録として曖昧になりがちです。
「図る」と「取る」を使い分ければ、今は整え中か/もう獲得したかが一目で分かり、合意形成やタスクの引き継ぎもスムーズ。
小さな言い回しですが、信頼される文章への近道です。
ビジネス・日常の実例集(置き換え辞典)

ビジネス定番フレーズ(プロセス↔結果の対比)
「合意形成を図る/合意を取る」
「理解促進を図る/了承を取る」
「再発防止を図る/対策を取る」
「関係強化を図る/面談の機会を取る」
など、片方がプロセス、もう片方が結果の関係になっているものが多いです。
表にしておくと、社内での表現ゆれも減り、読みやすさが揃います。
日常会話の例(やさしい言い換え)
「少しお時間を取れますか?」「後日あらためて連絡を取ります」「家族で話し合い、理解を図ってから決めます」など、家庭や友人との会話でも使い分けが活躍します。
特に女性同士のやりとりでは、気持ちに寄り添いながら進める表現が喜ばれます。
結果を急がず、まずは気持ちや状況の共有から始めると、自然に「図る」が選べます。
文化・地域の違いにやさしく配慮
地域や業界によっては「連携を取る」が日常的に使われます。
否定するより、文体と場面で使い分ける姿勢が大切です。
公的文書や外向き資料では「連携を図る」、内々のチャットでは「連携を取る」のように切り替えれば、角が立たず伝わります。
相手の慣れた言い回しを尊重しつつ、自分の文章は軸を持って整えるのがコツです。
ケーススタディ(メール・会議・報告書)
メール:依頼・相談・報告の書き分け
依頼メールでは「まず理解促進を図りたく、背景共有のお時間を取れますか」と図る+取るを上手に合わせると丁寧です。
相談では「合意形成を図るため、関係者で短い打合せの場を取りたいです」。
報告では「再発防止を図る施策を実施し、必要な承認は順次取っています」。
目的と結果が切り分けられ、読み手が迷いません。
会議:議事録とアクションの整合
議事録では、目的欄に「品質向上を図るための取り組みを検討」と書き、アクション欄に「ユーザー代表の了承を取る」と明記します。
こうして図る(目的)/取る(結果)を並べると、チーム全体で状況が共有しやすく、次回会議での確認もしやすくなります。
小さな工夫ですが、合意の取りこぼしを防ぐ効果は大きいです。
報告書:目的と結果を段落で分ける
報告書では、まず「本施策は関係強化を図ることを目的とする」と明記し、次に「アンケートの回答を取り、許可を取った上で実行」と続けます。
目的と結果を段落で分けるだけで、読み手は道筋を追いやすく、評価や承認も得やすくなります。
KPIの前後関係も明確になり、再現性の高い書き方になります。
誤用ランキング Top10 と瞬間修正ルール

よくある誤用をまとめてチェック
よく見かけるのは「×了承を図る」「×理解を取る」「×連絡を図る」「×休暇を図る」など。
いずれも結果・接触の名詞なので「取る」が正解です。
誤用は悪気なく起こりますが、読んだ人の解釈がズレてしまうことも。
まずは名詞の性質に注目し、受け取る性質か、整える性質かで判断しましょう。
if-thenで一瞬判断(小さなマイルール)
if 相手から承認や連絡を得る → 取る
if 関係や状態を良くする → 図る。
この2行を画面の付箋にしておくと便利です。迷ったら立ち戻れる“ホームポジション”があると、表現が安定して読みやすくなります。
特に新人さんの文章レビューでは、このルールでやさしく指摘してあげると、ぐんと理解が深まります。
一括置換のコツ(校正を時短)
納品前や配布前に、「了承を図る→了承を取る」「理解を取る→理解を図る」などの置換リストでサッと見直すと安心です。
併せて同音語(測る/計る/量る/図る)や変換ミス(採る/取る/撮る)もチェック。
表現ゆれを整えるだけで、文章全体の印象がぐっと上がり、読み手への思いやりも伝わります。
まとめ:効果的なコミュニケーションを図るために
要点3行まとめ
1)プロセス=図る
2)結果・接触=取る
3)文体と場面で最終調整。
——たったこれだけで、メールも議事録も驚くほど読みやすくなります。
まずは今日の1通から試してみましょう。小さな積み重ねが信頼される文章を育てます。
この記事を活用するコツ
迷ったときは、このページを辞典のように開いてください。
似た表現の対比を確認し、置換ルールで素早く修正すればOK。
大切なのは、相手が受け取りやすい言葉で丁寧に伝える気持ちです。自分を責めず、少しずつ整えていきましょう。
さらなる学びへのヒント
次のステップは、よく使う社内メールのテンプレを作っておくこと。
依頼・相談・報告の3種類があれば十分です。
本記事の軸に沿って言い回しを整理すれば、時短と品質アップを同時に叶えられます。


